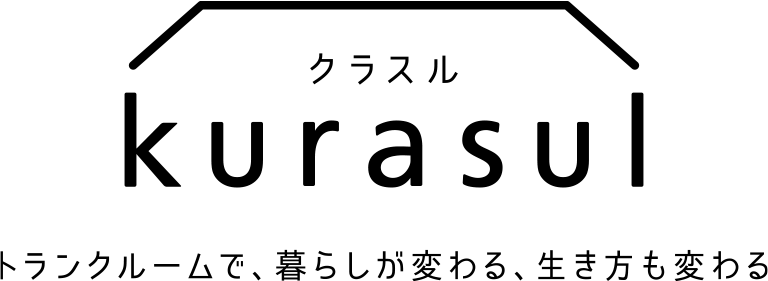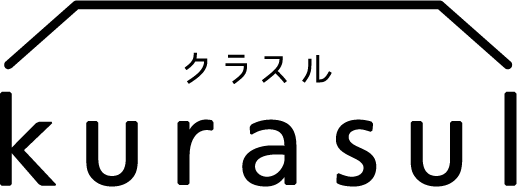本の断捨離の手順を徹底解説!残す基準と捨てる基準も含めて紹介
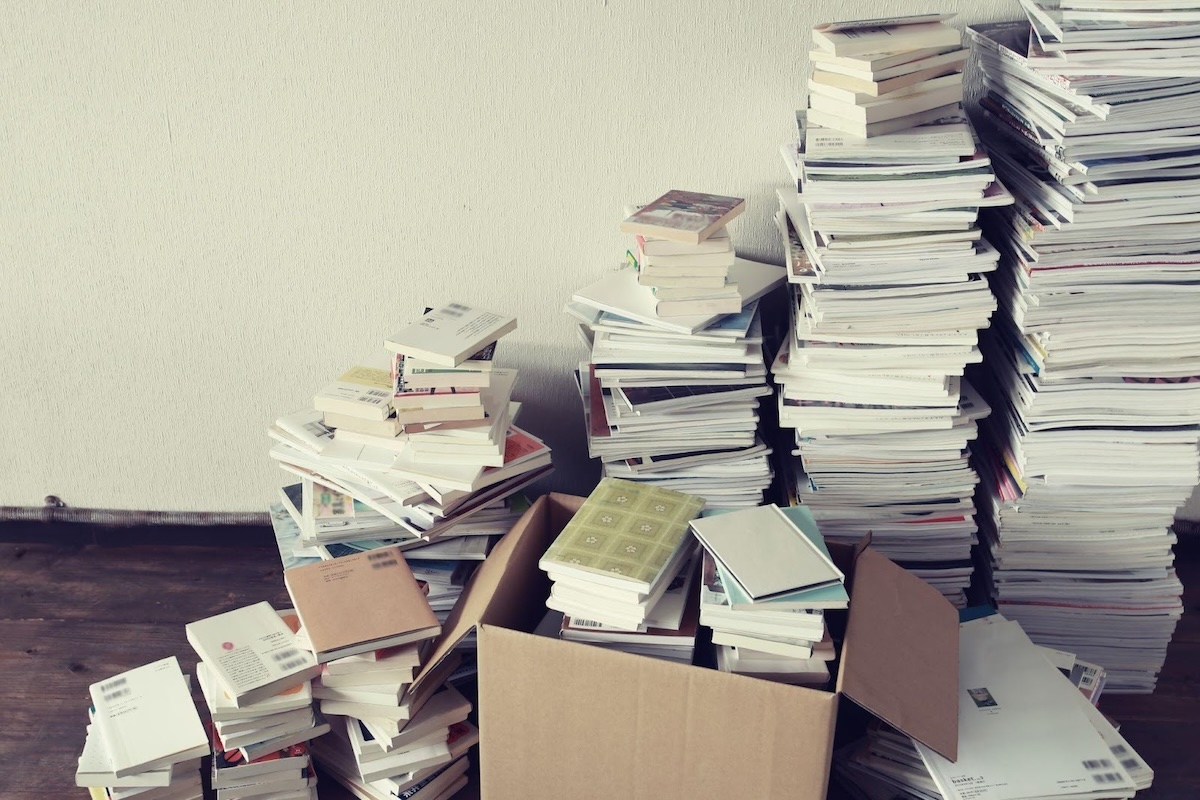
本棚が本でいっぱいでお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。思い切って本の断捨離をしたいけれど、手順が分からないという方もいるでしょう。
この記事では、本の断捨離をスムーズに進める手順やコツ、残すべき本の基準、捨てるべき本の基準を解説します。また、断捨離をするか悩む本の一時置き場に役立つトランクルームも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【ハローストレージでトランクルームを探す(全国で12万室以上展開中)】
本の断捨離の手順
本が増えすぎて困っているという場合は、本の断捨離に取り組むことも選択肢の1つです。その際は、以下の手順で断捨離の作業を進めてみましょう。
- 本棚からすべての本を出す
- 本を仕分けする
- 本を処分する
- 残す本を本棚に戻す
- 本が多い場合はトランクルームも検討
ここでは、ステップごとに解説していきます。
1.本棚からすべての本を出す
まずは、自分が持っているすべての本を出すところからはじめましょう。本棚や収納ラック、押入れなどにしまってある本を、床やテーブルなど、本の量が把握できる1か所に集めます。
このように持っている本を1か所に集めることで、手持ちの本の量を視覚的にとらえることが大切なポイントです。
2.本を仕分けする
集めた本は、仕分けの作業を行います。本の仕分けは「残す」「捨てる」「保留」の3分類で進めるようにします。
ここで重要なのが、「残す」「捨てる」の基準を事前に決めておくことです。基準を決めることで、仕分けの判断もスムーズに進めやすくなります。なお、断捨離の基準については、後ほど紹介します。
また、基準を決めていてもどうしても判断に悩むこともあります。その場合は、じっくり考えるのではなくひとまず「保留」としましょう。「保留」とした本は、後日改めて検討すれば問題ありません。ただし、保留したままにならないように、3か月から半年以内に再検討するなど、期限を設けておくことが大切です。
3.本を処分する
捨てる本が決まったら、適切な方法で処分しましょう。通常のゴミとして出す場合には、自治体のルールに従って処分することが大切です。自治体にもよりますが、本は一般的に資源ゴミとして処分することが多いです。
また、状態がよい本であれば、古書店や宅配買取で売却する、フリマアプリ、オークションサイトなどに出品する方法もあります。売却できそうにない本は、寄付や譲渡する方法もあるため、検討してみましょう。
4.残す本を本棚に戻す
「残す」に分類し厳選された本は、本棚に戻します。その際のポイントは詰め込みすぎず、本棚の7〜8割程度にすることです。
本を詰め込んでしまうと、本が傷んだり破れたりしやすくなります。また、湿気がこもってカビや虫が発生したり、本の出し入れが困難になったりもするでしょう。本を収納する際は、スペースに余裕のある状態で行うことが大切です。
残す本が多すぎて本棚に入れるスペースがない場合は、後述するトランクルームの利用もおすすめです。
5.本が多い場合はトランクルームも検討

断捨離をしても、本が多すぎて本棚などの収納スペースが足りない場合は、トランクルームを検討してみましょう。
トランクルームとは、自宅の収納の延長として利用することができる収納サービスのことです。処分したくない本や、普段は読まないけれど捨てられない本などをトランクルームに収納することで、本棚や自宅のスペースにゆとりをもたせることができます。
また、自分専用の書庫として使用できるため、大切な本を処分したくないのであれば、利用を検討してみるとよいでしょう。
本を収納するのであれば、空調設備が整っていることの多い屋内型トランクルームが向いている場合が多いといわれています。ただし、空調設備だけでなく、自分で湿気対策や防虫対策をすることも忘れないようにしましょう。
【トランクルーム利用例】

【ハローストレージでトランクルームを探す(全国で12万室以上展開中)】
関連記事:トランクルームとは?使い方や選び方、メリットを徹底解説
関連記事:本が多い部屋の収納のコツは?収納前にすることや収納アイテムを解説
本の断捨離の「残す基準」
前述しましたが、本の処分をスムーズに進めるために、断捨離する際の基準やルールを決めておくことが大切です。ここでは、本を「残す基準」の参考例として以下の4点をご紹介します。
- 思い入れのある本
- 将来役立つ本
- 1年以内に読んだ本
- 内容が貴重な本
1つずつ紹介していきます。
思い入れのある本
思い入れのある本は、「残す」と決めておくことをおすすめします。たとえば、小さい頃の思い出の本、人生の転機となった本、大切な人からもらった本などは、今は読んでいなかったとしても、かけがえのないものだといえるでしょう。
本を手に取ってみて思い出がよみがえる、処分したくないと思うのであれば無理に捨てる必要はありません。自分にとって大切な本は、「残す」としておきましょう。
将来役立つ本
今後の仕事や勉強で必要になる、資料として役立つと感じる本は残しておくとよいでしょう。どのような転機が訪れるかわからないため、少しでも将来の自分に価値があると思われる本は、残しておきましょう。
1年以内に読んだ本
1年以内に読んだ本は、処分せず残しておきましょう。今後も読む可能性が高いため、残しておくことで後悔しにくくなります。
一方で、1年以上読んでいない本は、今後も読む可能性が少ないかもしれません。ただし、前述したように思い入れのある本についてはよく考えてから判断しましょう。
内容が貴重な本
内容が貴重な本や歴史的に価値のあるような本は、残しておいたほうがよいかもしれません。
絶版になっているような本を処分してしまうと、再度入手するのは困難です。希少価値があるか分からない場合は、インターネット検索などを活用して、どういった価値がある本かを確認するのもおすすめです。
本の断捨離の「処分する基準」
続いて、本の断捨離の「処分する基準」の参考例について見ていきましょう。ここでは、以下の4点をご紹介します。
- 状態が悪い本
- 情報が古い本
- 読みかけて挫折した本
- 電子書籍がある本
「残す基準」とあわせて、参考にしてみてください。
状態が悪い本
表紙や中の破れや汚れがひどい、ページが欠けている、水濡れして跡がついているなど、状態が悪い本は処分の対象としてもよいかもしれません。
同様に、文字が薄くなり解読が難しい本や、紙魚(シミ)が発生している本も思い切って処分を検討しましょう。紙魚(シミ)とは紙を餌にする害虫で、書籍などが食べられてしまうことがあります。
ただし、状態が悪かったとしても、前述したように内容が貴重な本の場合は、処分すべきかどうかよく検討しましょう。
情報が古い本
情報が古くなりやすい本には、雑誌や旅行本、辞書などがあります。数年前のもので情報が古くなっているようであれば、思い切って処分し、最新のものに買い替えるとよいでしょう。
また、現在の自分に合わなくなった、価値観が変わって共感できなくなった本も処分を検討してみることをおすすめします。情報や内容の古い本を処分することで、現在の自分に必要な本だけを残せるようになります。
読みかけて挫折した本
読みかけて挫折してしまった本が、もしかしたら手持ちの本の中にいくつかあるかもしれません。こうした本は、断捨離のタイミングで今後読む可能性があるか考えてみましょう。
処分したくない場合は、すぐに読み始めるのも方法の1つです。今は読む気にならないからと先送りにすると、結局読まないで終わることも少なくありません。
もし、読み切っていない本を処分するのに抵抗があるようであれば、「保留」としてみても問題ありません。ただし、保留期間を設けたうえで、期間を過ぎても読まなかった本は処分するという潔さも大切です。
電子書籍がある本
電子書籍化されているのであれば、断捨離のタイミングで電子書籍に切り替えるのも1つの方法です。
コミックや小説は電子書籍になっている場合が多く、特にコミックは冊数が増えやすいため、電子書籍にすることで本棚をスッキリさせやすくなるでしょう。収納スペースをとる写真集や美術書も、場合によっては電子書籍化されていることがあります。
処分したくないけれどスペースを取っている本があれば、電子書籍化されているかチェックしてみるとよいでしょう。
本の断捨離で収納場所に困ったらトランクルームも検討しよう
ここまで、本の断捨離をスムーズに進める手順やコツ、残すべき本の基準、捨てるべき本の基準を解説してきました。本の断捨離は正しい方法で行い、事前に「残す基準」「処分する基準」を決めておくことが大切です。
また、断捨離をしても本棚がいっぱいで入りきらない場合や、すぐには読まないけれど思い出があって処分できない本が多い場合は、一時置き場としてトランクルームの活用もおすすめです。
本を収納するスペースが足りなくてお困りの方は、トランクルームを第2の本棚として活用してみましょう。
トランクルームならハローストレージ
レンタル収納スペース「ハローストレージ」なら全国に2,500物件以上・12万室以上展開中です。お客様のご利用用途に適した商品タイプ・大小さまざまなサイズのお部屋をご用意しています。
皆様に安心して使っていただけるよう、警備会社によるセキュリティや、定期的な巡回もしております。トランクルームを検討している方は、掲載物件数 No.1(※)の「ハローストレージ」をご検討ください。
※2022年3月期 指定領域(※)における市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1
※「指定領域」=レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社(エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位8社)を対象として、物件数を No.1 検証調査
全国のトランクルームを探すにはこちら
https://www.hello-storage.com/list/

監修
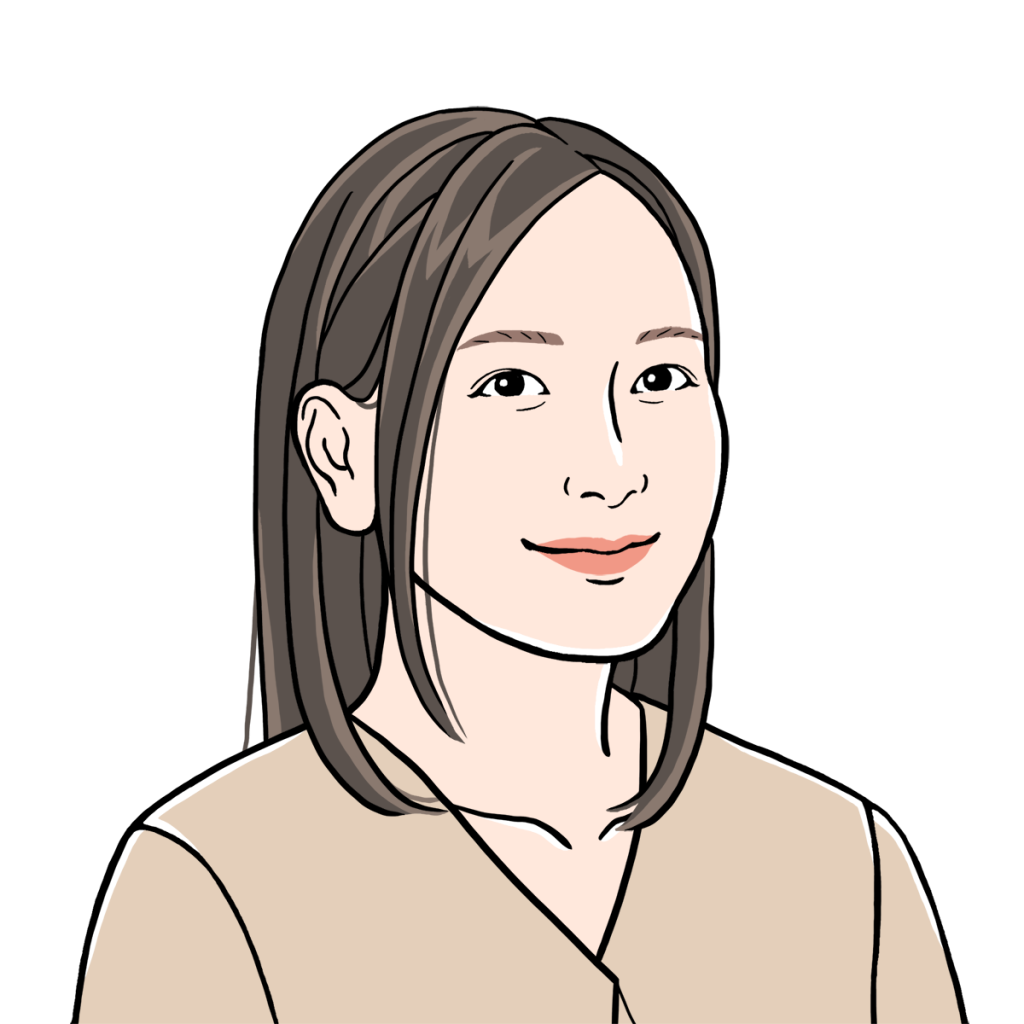
エリアリンク株式会社 マーケティング部
小川 真澄
2020年 整理収納アドバイザー2級 取得
2022年 整理収納アドバイザー1級 取得
2024年 防災士 取得
子どもの時からお片付けや断捨離は大の苦手。整理収納アドバイザー2級の勉強を機に、お片付けには理論やセオリーがあり、身の回りを整理整頓すると生活がかなり快適になることに感動。お片付けのプロになりたいと思い立ち1級を取得。
災害大国の日本でお家の整理収納は非常時にも役立つという思いもあり、本格的に防災について学ぼうと防災士を取得。
大切な物を捨てずとも、整理収納 × 防災 × トランクルームで、より暮らしやすい生活を提案するために日々奮闘しています。